ボイラー実技講習
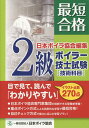
- ボイラー実技講習
- ボイラー実技講習会は受講料がめちゃ高
- 平成28年8月1日 ボイラー実技講習1日目(於 JA岡山ビル)
- 平成28年8月2日 ボイラー実技講習2日目 (於 JA岡山ビル)
- 使用テキストがダメ
- 受験準備講習も多分期待できないだろうな
- 実技講習の位置づけが不明確
- 社会人でもさほど高校生と理解度は変わらない人も多いのでは ?
- 平成28年8月4日 実技講習3日目(於 岡山港湾福祉センター)
- パソコンシュミレーターの実習は25年前ならまあまあ先進的かな
- パソコンシュミレーターの自由度はそれほどない
- かつて日本ボイラ協会が販売していたシュミレーションソフト
- 実際のボイラーを使っての実習
- 余った時間は『ボイラー実技テキスト』での復習
- 免許を取得するためには絶対に受講しなければならない講習だから
ボイラー実技講習
ボイラー実技講習会は受講料がめちゃ高
昨年12月に合格した2級ボイラー技師の実技講習を受けてきました。2級ボイラー技師は試験に合格しても、実務経験がなければ、この実技講習を受けないと免許がもらえないんです。
しかしこれの受講料が、岡山では18,000円。今年値上げされたみたいです。これだけお金がかかるとも知らずボイラーを受験したので、かなり痛いです。
(2級ボイラー免許証総取得経費はこちら)
平成28年8月1日 ボイラー実技講習1日目(於 JA岡山ビル)
講習の最初に、すでに試験に合格している人に挙手をさせた様子を見ていると、6人手が上がったようなので、今回岡山では67人の参加で、合格してから実技講習に来ている人は10人も居ないのかもしれません。
私のように合格していても手を上げない人もいるかもしれないので、どれくらいなのか、正確なところはわかりませんが。
講習申し込み時に、合格済みかまだかを申請しているのだから、講師ならその情報ぐらいはきちんと把握してから、講義に臨んでほしいものです。
(協会の人によれば、この合否は任意記述だから、数は把握していないということでした。何のために書かせているのやら)
1日目を受けた段階では、この講習を試験合格後に義務付ける意味が理解できませんでした。試験で問われるような部分の内容の確認を延々と1日聞かされただけでした。9時から5時まで。
しかも、受験にも役立つように、きちんと一歩一歩内容を整理して提示してくれるのなら、復習としても、試験の予習としても役に立つのですが、例えば、「炉筒」「煙管」という言葉を説明せずに、いきなり、「丸ボイラー」「縦ボイラー」「炉筒煙管ボイラー」「貫流ボイラー」などの用語を立て続けに使って説明していくのですから、試験用の勉強をして、自分である程度整理して理解した人でない人が、これをいきなり聞いても、やっぱりほとんど理解できず、ストレスを抱えたまま、我慢して座っているしかありません。ですから、受験のためにも役立つとは思えません。
復習用としても、基礎を押さえずにいきなりピンポイントの要点だけですから、そのもとになるところを確認するといったこともできないまま、次へ次へと進んでしまいます。
平成28年8月2日 ボイラー実技講習2日目 (於 JA岡山ビル)
相変わらず、『ボイラー実技テキスト』と『ボイラー図鑑』を使っての講義。この2日間で、『ボイラー実技テキスト』の全内容を講義するようになっています。
今日は9時から昨日より1時間早い16時まで。途中5分休憩4回、昼食の40分休憩という時間割です。
今日も昨日とは違う講師が、午前・午後で入れ替わって、2日間で計4人のうち3人が日本ボイラ協会作成のパワーポイントを使っての講義でした。
しかし相変わらず、「ブロー」とか「フロート」とか門外漢にはイメージがない専門用語を当然分かったものとしてふんだんに使う講義なので、何もわからない人間が、講義を聞いてイメージをきちんと持てるようになることなど期待しようもありません。
内容的には、「6.点検及び異常時の処置」については、テストにもあまり出ず、『最短合格2級ボイラー技師試験「技術科目」 目で見て、読んで「わかりやすい」』にも詳しくは記載されていない内容だったので、多少面白く聞くことができました。
また今回は、『最短合格2級ボイラー技師試験「技術科目」 目で見て、読んで「わかりやすい」』を持って行ったので、疑問に思ったことをその場で調べることができ、だいぶストレスが軽減されました。
使用テキストがダメ
講習会では『ボイラー実技テキスト』『ボイラー図鑑』というのが強制的に買わされるテキストです。
『ボイラー図鑑』は、文字通り図鑑で、ボイラー関係の写真や図が大きく掲載されています。これだけ大きな写真や図は、他ではたぶん手に入らないと思うので、絶対に必要かと言われれば、そうとも言えませんが、あればあったなりに見る要素はあると思います。
ただし、この本は説明が全くないので、独学用としては使えません。
それと、もう一つの『ボイラー実技テキスト』はいけません。説明が全部ベタ打ちのメリハリのない文章だけですし、理解しなければならないポイントの説明も抜けています。
講習では、これら2冊から要点を抜き出して、黄色のマーカーをしたり、テキストで抜けているいる部分を補ったりして、結構よいパワーポイントの画面を提示してくれました。
でも、これをなぜ講義資料として配布してくれないのでしょうか。
このパワーポイントで補っている部分が大切なのに、テキストは見にくいし、そこに書かれていないところを自分で書き写すのにも時間はありません。
せっかくいいパワーポイントの資料を作っているのに、画面だけをちょっと見せて、結局自習用には使わせないのでは、受講自体が全くの無意味になってしまいます。
それぐらい、この資料を配布してくれないことは致命的で、それが講習の価値をよくも悪しくも決定的に決めてしまうぐらいの大切な問題であると私は思いました。
ちなみに、このパワーポイントの資料は、やはり日本ボイラ協会が作っているものだそうで、それに各講師がオリジナルの部分を少し付け加えているようでした。
日本ボイラ協会の方針で、配布はできないのだそうです。
このパワーポイントの資料のようなとってもいい本を作る能力があるのですから、『ボイラー実技テキスト』のような前世紀の遺物のような使いようのないテキストは早々に廃刊にして、このパワーポイントの資料を基に、『ボイラー実技テキスト』を編集し直した方が、よっぽど世の中のために役立つと思います。日本ボイラ協会には、受講者の立場で考えてほしいものです。
受験準備講習も多分期待できないだろうな
今回の1・2日目の講師4人は、いずれも企業出身で、うち3人は、もう10年以上実技講習の講師をなさっているようです。
中には多少関連知識を交えて講義をしてくださる方もいましたが、しかし全体に語り口が単調で、全くイメージを持っていない門外漢にもわからせてやろうという意気込みは感じられないので、特に午後からの講義では、どうしても眠くなってしまいます。
他にも中には突っ伏して寝ている方も居て、それでも注意せずにそのままですし、講習修了試験はなしで、講習修了資格は一生有効ですから、ボイラーの実技講習自体、その程度の位置づけでしかないんでしょう。こんな調子の講習ですから、受験準備講習も同じような講師なら、それほど期待できそうにはありません。
『お勧め参考書など』に書いた、講義や本を使って独学するほうが、時間をかけずによっぽど濃い内容が身につくのではないでしょうか。
ただし、ボイラー協会の人の言い分によれば、実技講習は試験対策ではなく、あくまでも事前講習的な位置づけで、受験準備講習では、試験の過去問が、いつどんな形で出題されたかがわかる詳細な資料が提供されるので、試験の役に立つという話でした。
実技講習の位置づけが不明確
2日目にボイラー協会の方と話をして、先述の、「実技講習が実技の講習に全くなっていず、試験の内容の大雑把なまとめ程度にしかなっていない」というような話をしたところ、「元々受験前に受講を義務付けられていた講習の流れをくむものだから、合格者を対象にした講習にはなっていない」というようなことを言われました。
しかし、それなら、まだ試験に合格していない人に対して、「ボイラー」というもののイメージを全く持っていない状態から、少しでも試験に対応できるようなイメージを持たせるための努力がいるのではないでしょうか。
全くイメージを持たせる努力をしないまま、試験で問われそうな箇所を所々つまんで用語の説明をせずの解説では、受験準備としても、試験合格後の実技指導としても、全く役には立ちません。
受験前の人を対象の講習にするつもりなら、それはそれでも仕方がないので、もうちょっとそれ用の意義ある講習にしてもらえないでしょうか。
社会人でもさほど高校生と理解度は変わらない人も多いのでは ?
講師の方が、安全弁の保守の説明で、コンパウンドを使っての弁体と弁座のすりあわせを説明するときに、「これを高校生に説明しようとするととても時間がかかるから、実物を持って行ったりして大変だが、今日の人たちは、これぐらいの説明で分かるだろうから」というようなことを言っていました。
確かに高校生は実体験が少ないとはいえ、社会人でも車とか機械とかをいじった経験がない人なら、このような簡単な説明だけでは理解できないかもしれないというのは、高校生とさほど変わらないのではないでしょうか。
ボイラーの実務経験がない人たちが受ける講座なのですから、ボイラーや機械についての実物のイメージを持っていることを前提とした説明というのはいかがなものでしょうか。
「コンパウンドというのは、きめの細かい堅い粒子を混ぜたもので、それを塗ってすりあわせて磨くことで、弁の密着度をよくする」というぐらいの説明が、高校生ではなくとも必要なのではないでしょうか。
このようなちょっとした配慮をするかどうかで、説明のわかりやすさは全く違ってくるはずです。
平成28年8月4日 実技講習3日目(於 岡山港湾福祉センター)
3日目は場所を変えて、岡南飛行場近くの岡山港湾福祉センターという所でした。
座学でない実技講習は、1日40人定員ということで、3日目初日の3日に41人もう受講が済んでいるので、本日4日はあと残りの26人を2班に分けての講習でした。ボイラーを前にしての実地講習と、パソコンシュミレーターやボイラーの模型を使った実習とを、午前組と午後組とに分けていました。
講師は1日中同じ講師が担当しました。
遅く申し込んだおかげで、座学と実地講習とが1日間が空いて、ちょっと不細工な嫌な感じでしたが、実地講習の2日目の組になったおかげで、講習を受ける人数が前日よりかなり少なく、余裕のある時間で講習を受けることができたので、かえってその方がよかったです。
パソコンシュミレーターの実習は25年前ならまあまあ先進的かな
「パソコンシュミレーターでボイラーを爆発させた」という話をよく聞くので、期待をしていました。シュミレーターそのものは、よくありそうな簡単なプログラムで、そう変わったところはありませんでした。
が、パソコンの使い方は思っていたのとは違って、講師用のパソコンを使って、1人ずつ講師のところに行って、そのパソコンを操作しての実習でした。
もちろん操作した画面が、講習用前面パネル一面に、みんなが見えるように映し出されます。
パソコンが教育現場に普及してきた25年も前のころなら、それでも驚きませんが、今どき各人一台、せめて数人に1台のパソコンを想像するのが普通ではないでしょうか。
パソコンシュミレーターの自由度はそれほどない
シュミレーターの操作は、よく言えばシーケンス制御になっていて、設定が手動であっても、予定されたボタン以外を操作しても、ほとんど反応しません。
ですから、少々手順を間違っても、プログラムの反応がないだけで、そう簡単にボイラーが爆発することなどありません。
よく出来ているのかと、ちょっと期待しすぎでした。
パソコンシュミレーターは、ボイラー起動の手順と、水面計の点検時のコックの開け閉めでした。
ボイラー模型を使っての実技は、ボイラー起動の手順の確認です。
かつて日本ボイラ協会が販売していたシュミレーションソフト
今ネットで検索していると、「日本ボイラ協会が技術の粋を集めて制作、販売」したという、平成14年発売の一金25万円なりの、ボイラーのシュミレーターの広告を見つけました。さすがに今は販売をやめているようですが、ホームページにかつて売っていたであろうと思わせる残骸が残っています。(ホームページ移転に伴って、ついに削除されてしまったようです)
これを一人に一台ずつ、2時間ほど一人で使って遊ばせてくれる方が、よっぽど面白い効果があるのではないでしょうか。
今協会が講習で使っているソフトは、広告を見る限り、これよりもっと簡易的なもののような気がします。
実際のボイラーを使っての実習
実際のボイラーを使っての実習は、間欠吹出しの手順を、一人ずつ順番に行いました。
ここに置いてあるボイラーは、人の高さぐらいのもので、どこかの企業で使われていて、もういらなくなったやつをボイラー協会が手に入れて、実習用に据え付けたもので、蒸気や吹き出した排水は裏の道路に垂れ流しでした。
年に数回数時間、人通りの少ない場所とはいえ、一般の方が通るかもしれない道路に、100度近くある水や蒸気を垂れ流すのは、ちょっと危ない気がしました。
ここにボイラーを据え付ける前は、岡山駅で実習をやっていたそうです。
余った時間は『ボイラー実技テキスト』での復習
ボイラーを実際に操作して余った時間は、『ボイラー実技テキスト』を使って、今日やった範囲の復習でした。
このとき、ボイラー関係の部品の実物をだいぶ見せてくださったのは、よかったです。『ボイラー図鑑』の写真は大きくて、同じものが結構大きく写真になっていても、やはり実物を手にして、ちょっとだけでも解説を聞いたおかげで、『ボイラー図鑑』を後から見ても、だいぶどんなものかが実際の感覚を伴って分かるようになった気がします。
免許を取得するためには絶対に受講しなければならない講習だから
2級ボイラー技師の免許を取得するためには、実務経験がない者は、どうせこのバカ高い実技講習を受けなければなりません。
試験に受かった後で改めてこれを受講してもほとんど無意味なので、2級ボイラー技師の免許を目指して何がなんでも絶対にこの資格を取得するつもりなら、ある程度学科を自分で勉強しておいてから、受験前にこの講習を受けたほうが、まだ少しでも受講が役に立つ可能性はあります。
でも、途中で挫折して免許申請をするまでに至らない可能性があるのなら、前もってこれだけの大金を払うのはちょっともったいないかもしれません。
